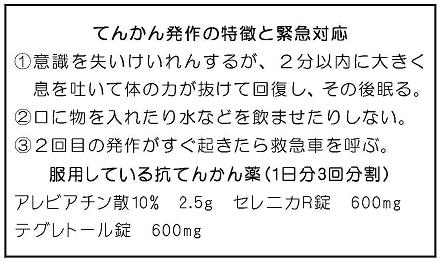改訂版の発刊にあたって
日本てんかん協会栃木県支部は2007年に設立20周年を迎えることができました。これを記念して、多くの皆様にてんかんについての理解を深めていただけたらと思い、小冊子を発刊いたしました。
今年3月11日には東日本大震災で大きな被害があり、従来の防災マニュアルの見直しが必要といわれています。また、4月18日には、栃木県内で発作が抑制されていないまま不正に免許を取得した運転手による事故で学童6人が亡くなりました。てんかんのある人は、発作の状況が一定基準を満たさないと、自動車運転免許などいくつかの資格や免許が取得できません。そのため、多くのてんかんのある人は自己管理と治療に努力しています。しかし、この事故をきっかけに、てんかんのある人は危険という偏見が広がり、正式に免許を取得したり病名を告知して採用された職場でも差別ともいえる理不尽な扱いが起きてしまいました。てんかんについて理解があれば起きなかったものです。
そこで、多くの皆様にてんかんを正しく理解していただき、てんかんのある人も充実した生活が送れるように支えていただきたいと考え、防災対応と運転免許についての内容を追加し、改訂版を発刊することにしました。
ぜひ、この小冊子をご覧になり、てんかんを一層ご理解いただき、さまざまな場面でご協力くださいますようお願いします。
2011年11月1日
今年3月11日には東日本大震災で大きな被害があり、従来の防災マニュアルの見直しが必要といわれています。また、4月18日には、栃木県内で発作が抑制されていないまま不正に免許を取得した運転手による事故で学童6人が亡くなりました。てんかんのある人は、発作の状況が一定基準を満たさないと、自動車運転免許などいくつかの資格や免許が取得できません。そのため、多くのてんかんのある人は自己管理と治療に努力しています。しかし、この事故をきっかけに、てんかんのある人は危険という偏見が広がり、正式に免許を取得したり病名を告知して採用された職場でも差別ともいえる理不尽な扱いが起きてしまいました。てんかんについて理解があれば起きなかったものです。
そこで、多くの皆様にてんかんを正しく理解していただき、てんかんのある人も充実した生活が送れるように支えていただきたいと考え、防災対応と運転免許についての内容を追加し、改訂版を発刊することにしました。
ぜひ、この小冊子をご覧になり、てんかんを一層ご理解いただき、さまざまな場面でご協力くださいますようお願いします。
2011年11月1日
日本てんかん協会栃木県支部


 目 次
目 次 ※ 印刷版(A5サイズ、本文28ページ)が必要な方は栃木県支部までご連絡ください。支部行事の会場では無料で配っていますので、ぜひ一度ご参加ください。
※ 印刷版(A5サイズ、本文28ページ)が必要な方は栃木県支部までご連絡ください。支部行事の会場では無料で配っていますので、ぜひ一度ご参加ください。 赤ちゃんからお年寄りまで
赤ちゃんからお年寄りまで
 意識を失い倒れてけいれんする発作だけではありません。さまさまなタイプがありますが、すべてのタイプの発作を一人の人がもっているわけではありません。その人によって発作のタイプは決まっています。発作が続く時間は、数秒のこともあれば、数分のこともあります。「重積発作」という特別な状態以外では発作そのものが致命的になることはめったにありません。
意識を失い倒れてけいれんする発作だけではありません。さまさまなタイプがありますが、すべてのタイプの発作を一人の人がもっているわけではありません。その人によって発作のタイプは決まっています。発作が続く時間は、数秒のこともあれば、数分のこともあります。「重積発作」という特別な状態以外では発作そのものが致命的になることはめったにありません。 全身の筋肉の緊張が高まり、頭部を前屈させる、両手を振上げる、両脚の屈曲させるという形をとる。
全身の筋肉の緊張が高まり、頭部を前屈させる、両手を振上げる、両脚の屈曲させるという形をとる。 ・単純部分発作
・単純部分発作 始まった発作は止められませんが、ほとんどの場合は数分以内に治まり自然に回復します。発作中は次のことに注意してください。
始まった発作は止められませんが、ほとんどの場合は数分以内に治まり自然に回復します。発作中は次のことに注意してください。


 発作が治まったら
発作が治まったら
 薬物治療
薬物治療 発作でけがをしやすい人は保護帽をかぶります。保護帽をいやがる場合には、帽子やバンダナの内側にフェルトを貼り転倒時の衝撃をやわらげる工夫をしたり、保護帽に手編みの帽子を重ねて使っている方もいます。また、かたい床にはショックを和らげるカーペットを敷くなどの環境の工夫も考えられます。
発作でけがをしやすい人は保護帽をかぶります。保護帽をいやがる場合には、帽子やバンダナの内側にフェルトを貼り転倒時の衝撃をやわらげる工夫をしたり、保護帽に手編みの帽子を重ねて使っている方もいます。また、かたい床にはショックを和らげるカーペットを敷くなどの環境の工夫も考えられます。
 発作時に発見が遅れる可能性があるので、海や湖では泳ぐのは避け、プールを利用しましょう。できればプールの監視員にてんかんであることを伝えておきましょう。
発作時に発見が遅れる可能性があるので、海や湖では泳ぐのは避け、プールを利用しましょう。できればプールの監視員にてんかんであることを伝えておきましょう。
 疲れすぎなければ大丈夫です。制限すると疎外感を与えかえってマイナスです。プールの中での発作をおこすことはまれで、水泳帽やパンツの色を目立つものにすることは、差別に敏感な子ならマイナスです。
疲れすぎなければ大丈夫です。制限すると疎外感を与えかえってマイナスです。プールの中での発作をおこすことはまれで、水泳帽やパンツの色を目立つものにすることは、差別に敏感な子ならマイナスです。
 人生最大のイベントともいわれるのが結婚です。多くのてんかんのある人は結婚し、とくに問題なく家庭生活を営んでいます。
人生最大のイベントともいわれるのが結婚です。多くのてんかんのある人は結婚し、とくに問題なく家庭生活を営んでいます。 抗てんかん薬の種類によっては、奇形をもった子どもが生まれる可能性はあります。出現する確率は一般の場合よりやや高くなります。このため薬の影響を怖がって服薬をやめてしまうと発作が悪化してしまいますので、妊娠する前から医師とよく相談しましょう。薬の種類や量の調整、催奇性を減少させる処方、外科手術の可能性の検討などを行います。
抗てんかん薬の種類によっては、奇形をもった子どもが生まれる可能性はあります。出現する確率は一般の場合よりやや高くなります。このため薬の影響を怖がって服薬をやめてしまうと発作が悪化してしまいますので、妊娠する前から医師とよく相談しましょう。薬の種類や量の調整、催奇性を減少させる処方、外科手術の可能性の検討などを行います。